2008年07月27日
味がわかる...豊かな食文化を
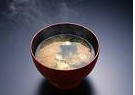
私達は、口にする食べ物に対して遺伝子的に多くのレセプターが用意されています。
総数3万種類といわれる遺伝子の総数のうち1,000以上の遺伝子が嗅覚や味覚に振り当てられてるといわれます。 それは、私達がよりよい食を見つけ香りをかぎ、味わうために実に多くの遺伝子資源を保有していることに他なりません。
大切なことは、味や香りを受ける応答は、決して単純な比例構造ではなくて、非線形型ということです。
強い刺激がある一定のレベル(閾値)を越える応答は敏感に動くのですが、それが大きくなりすぎると応答は全く鈍くなってしまいます。 味が濃かったり、塩分が多い食事を続けていると、その閾値が上がって、精妙でたおやかな味覚を関知することが困難になってしまいます。
ワインには、100ミリリットルあたり100㎎以上のカリウム塩が含まれているので、それを日常お茶代わりに飲んでいるヨーロッパの人達は、味の濃い、こってりした、塩濃度の高い料理でないと物足りないと感じるといわれます。
味覚も嗅覚も、音感や聴覚と同じように子供のある一時期に「クリティカルピリオド」があります。
特に子供の頃は、味覚や嗅覚は弱い刺激レベルの感覚受容を開いておくことが、豊かな味覚の基礎を作ることになります。
幼いときからファーストフードの濃いあじを食べ続けると、和食のように精妙な味の違いはわからなくなってしまいます。
若い方には、ご飯の硬さや軟らかさはわかるけど、どんな銘柄でもお米の味はなにもわからないという方が増えています。
もう一度、豪華でなく、昔からの素朴な日本の食文化を取り戻して欲しいように思います。
Posted by アリア at 11:59│Comments(0)
│日記











 Copyright(C)2025/森の小さなアイス屋 ALL Rights Reserved
Copyright(C)2025/森の小さなアイス屋 ALL Rights Reserved